こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!
「結婚後は医療事務のパートとして働きたいな…。」
「家庭との両立ができる、働きやすい医療事務の仕事っていいな…。」
女性に人気の職業として名高い医療事務ですが、その理由の1つには、結婚後、主婦になってからでも働きやすい点が挙げられます。
ここでは、結婚などで生活環境が変わっても働きやすい医療事務についてお話します。

本記事を読めば、「医療事務になりたい!」という気持ちが高ぶること間違いなしですよ!
4分でサクッと読める内容です。最後まで楽しんでご覧いただければ嬉しいです。
それでは、どうぞ!
もくじ
解説ショート動画:医療事務は結婚後も続けられる7つの理由
この記事の内容は、以下のYouTubeショート動画でも解説しています。サクッと動画で内容を確認したい方におすすめです。
医療事務は結婚後も続けられる理由7選
誰が何と言おうと、医療事務は結婚後も働ける仕事です。その理由は、主に以下の通りです。
- ①産休や育休がある
- ②さまざまな勤務形態がある
- ③女性に理解がある職場である
- ④病院は全国どこでもある
- ⑤雇用が安定している
- ⑥体力を必要としない
- ⑦30代〜50代の再就職先としても人気
誰でも理解できるように、カンタンな言葉で解説しますね。
理由①:産休や育休がある

結婚後も医療事務として働ける理由1つ目は、育休や産休が取れるからです。
将来的に出産や子育てを迎えるにあたり、育児休業や産前産後休業は知っておきたい制度の1つ。そもそも医療事務さんは「取得ができるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、医療事務さんも育休・産休は取得できます。
育休とは?
正式には”育児休業”と呼ばれ、子どもが1歳になるまで休むことができる制度です。
産休とは?
正式には”産前産後休業”と呼ばれ、「出産を予定している方」であればだれでも産前6週間~産後8週間のあいだ休むことができる制度です。
また、嬉しいことにパート・アルバイトや派遣社員といった雇用形態で勤務している医療事務さんも、条件を満たしていれば取得可能です。
- 同じ職場に1年以上勤めていること。
- 子どもが1歳を迎えた後も、雇用が継続される見込みがあること。
- 週2日以下の勤務でないこと。
このように、医療事務さんもほかの職業と同様にして、産休・育休が取れるため、結婚後に妊娠や出産を検討している方でも安心することができます。
理由②:さまざまな勤務形態がある
結婚後も医療事務として働ける理由2つ目は、多様化した働き方ができるからです。
医療事務は以下のように、様々な雇用形態があります。
- 正社員
- アルバイト
- パート
- 派遣社員
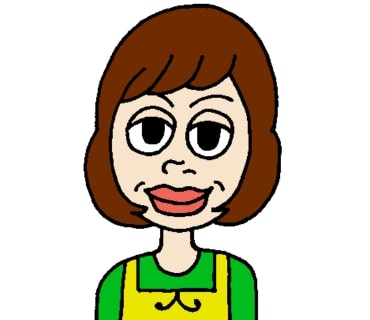
正社員だけではなく、パートアルバイトとしての求人も多く、活躍している女性はたくさんいます。
また、職場の医療機関の”規模”によっても勤務形態が異なります。
大規模な病院
例えば、大規模な病院であれば働くスタッフの数も多いので、「早番」「遅番」「日勤」などに分けられたシフト制による働き方があります。
小規模なクリニックや診療所
診療所やクリニックなどの小規模な医療機関では、診療時間が「午前診療」と「午後診療」とで分かれており、診療開始時間も医療機関によって異なります。
そのため、パートやアルバイトの場合は、「午前診療のみ」「午後診療のみ」「フルタイム」と働き方を選ぶことができます。
このように、医療事務は様々な雇用形態があることから、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
仕事と子育ての両立を願うママに適している職業と言えるでしょう。
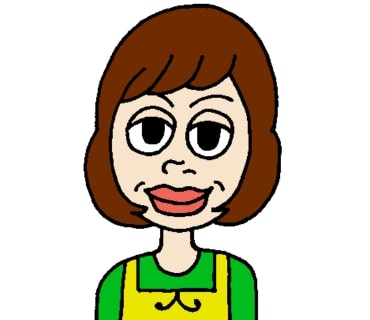
勤続年数が何十年にもなるという女性医療事務が、結婚していて子どもがいるというケースも珍しくありませんよ。
理由③:女性に理解がある職場である
結婚後も医療事務として働ける理由3つ目は、育児経験のある女性が多い職場環境だからです。
医療現場はなんといても、女性比率が高い職場です。(個人的な体感として1:9)
そのうえ、40代女性が最も活躍しているため、出産や育児を経験している女性が多いことも特徴です。
女性比率が高いことは、妊娠や子育てをするうえでメリットが豊富です。
- 妊娠中のつらさを分かってもらえる
- 子どもの急な体調不良に理解がある
- 育児に関する悩みを聞いてもらえる
同僚や先輩に、結婚後のイベントを相談できる&アドバイスをいただけることは、医療事務ならではの利点です。
理由④:病院は全国どこでもある

結婚後も医療事務として働ける理由4つ目は、復職しやすい仕事であるからです。
医療事務は、しばらく仕事を辞めても、復職しやすいという特徴があります。
なぜなら、一度習得したスキルは全国共通で普遍的に使えるからです。

正社員として勤務している場合
⇒待遇が良く、産休や育休を取得して復職する女性も多いでしょう。
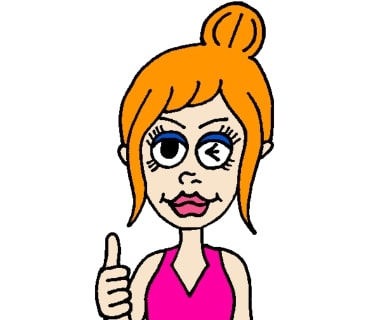
パートアルバイトとして勤務している場合
⇒経験者として優遇される。そのため、他の職業よりも仕事に復帰できる可能性は高いでしょう。
また、医療事務の職場は全国どこでもあります。令和元年5月時点の全国の病院の総数は179,208施設であり、このすべてが職場の可能性があります。
「結婚によって引っ越さなければいけない…。」
「出産により退職しなければいけない…。」
医療事務であれば、このような悩みも少なく、一生涯と通じて長く働ける仕事の1つと言えるでしょう。

転勤や転職は、資格があればラクにできるため安心ですね。
理由⑤:雇用が安定している
結婚後も医療事務として働ける理由5つ目は、不況に強い仕事だからです。
病院やクリニックで働く医療事務さんは生命に関わる仕事であるため、景気に左右されず安定してリスクが少ない傾向があります。
また、日本は高齢者が増加し続けている「高齢化」と、出生率が低下している「少子化」が2つ同時に進行している”少子高齢化”が加速しています。
そうなると、医療に携わるスタッフが減る一方、医療を必要とする高齢者が増加するため、これからニーズが増す仕事です。
近い未来、この傾向は変わることがないため、医療事務の仕事も安定していることでしょう。
理由⑥:体力を必要としない

結婚後も医療事務として働ける理由6つ目は、体力を必要とせず子育てと両立しやすいからです。
医療事務は基本的には、デスクワークで重労働ではありません。肉体を酷使することがないために、仕事を終えてからの家事や育児にフルパワーで尽くすことができます。

子どもと過ごす時間を大切にしたい方には、医療事務という働き方はオススメ!
一般的な医療機関では、暦通りの診療を行っています。
基本的に日曜日を休みとしているところが多いので、子育て中の人でも休日は子どもや家族との時間を過ごすことができます。
一般的な診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 |
| 14:30-18:00 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | 休診 |
また、ゴールデンウィークや夏季休暇、年末年始の休暇など、まとまった休みも取りやすいので、子どもの学校が休みになる長期休暇の間でも、子どもとの時間を取ることが可能です。
さらに、診療所などでよくある午前診療と午後診療の間にある長めの中休みの時間も、家庭のある主婦にとってはメリットのある時間です。
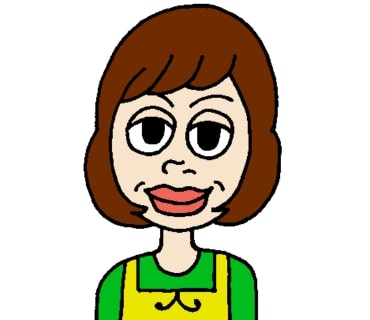
中休みでは、基本的に各自が自由に過ごすことができます。外出も可能であるため、自宅が近い人は1度帰宅すること方も多いでしょう。
中休みの間に1度帰宅することで、溜まった家事をこなしたり、夕飯の支度を済ませたりすることもできるので、時間を効率的に活用することができます。
理由⑦:30代〜50代の再就職先としても人気
結婚後も医療事務として働ける理由7つ目は、40代が最も活躍しているからです。
医療事務の年齢の中央値は40代。それは、結婚後に子育てがひと段落した後に医療事務になる人も多いことが理由の1つです。
未経験からでも人の役に立てる医療の仕事をすることができるため、チャレンジする方が多くいます。
「人と接する仕事がしたい!」
「手に職をつけて、安定して働きたい!」
「社会的に意義のある職業に就いたい!」
こんな風に考えているのであれば、あなたも医療事務にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
まとめ:結婚後も安定して働きたいのであれば、医療事務で決まり!
今回の記事では、医療事務が結婚した後でも続けられる理由について解説しました。
最後にこの記事をまとめます。
- 医療事務は結婚後も働きやすい環境である
- ブランクがあっても転職しやすい
- 医療事務は子育てママとの相性がいい!
医療事務にはさまざまな雇用形態と勤務形態があるため、仕事と家庭を両立しやすいです。
そのため、結婚して生活環境が変わっても医療事務として働き続けることが可能となります。
子育て世代のママにとって、「仕事と家庭を両立」できる仕事は、そう多くありません。
ぜひ、あなたも働きやすい仕事である医療事務にチャレンジしてみましょう。

この記事が、あなたの人生を一歩前へ進めることができる助けになれれば幸いです。
以上、元ヤン次女でした。
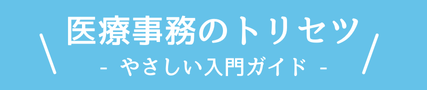
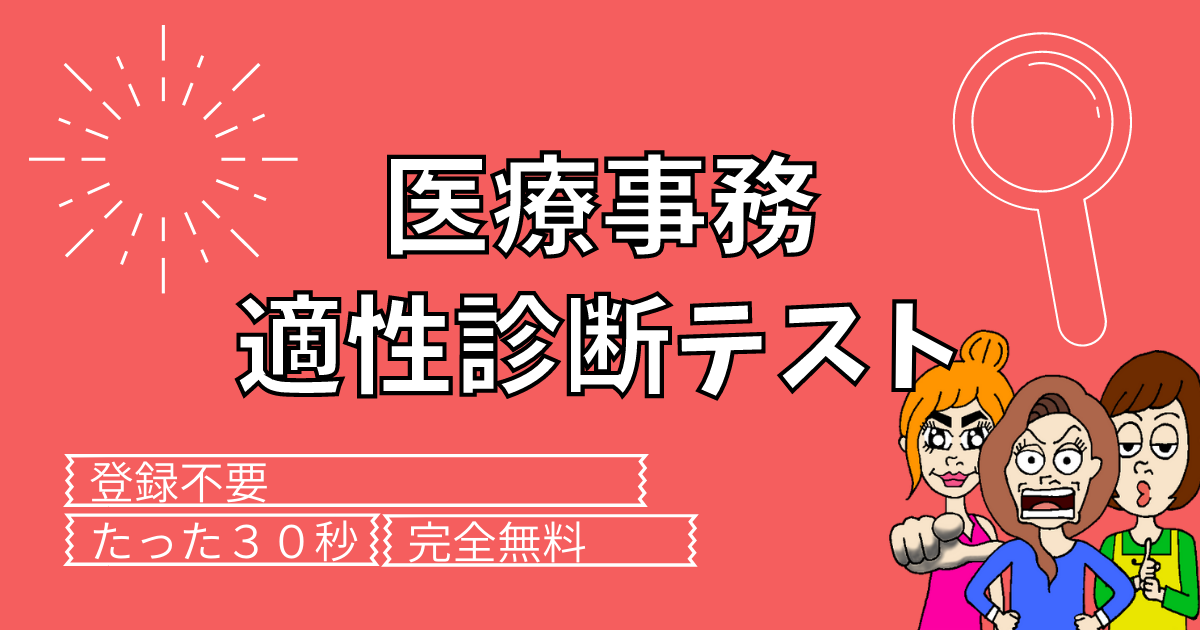
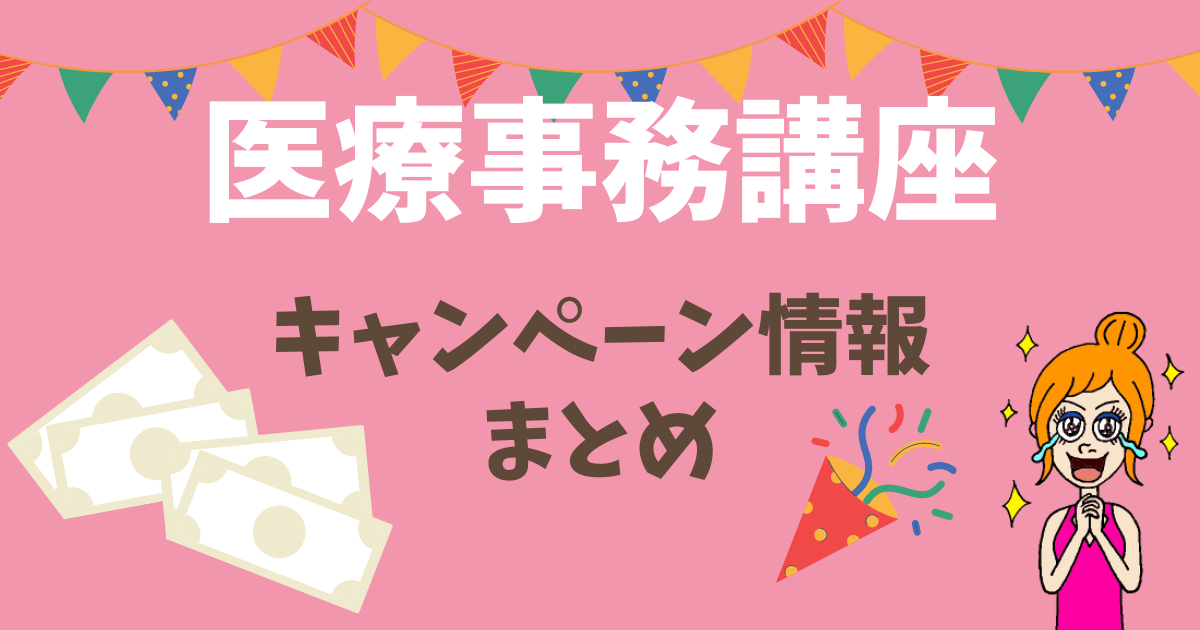


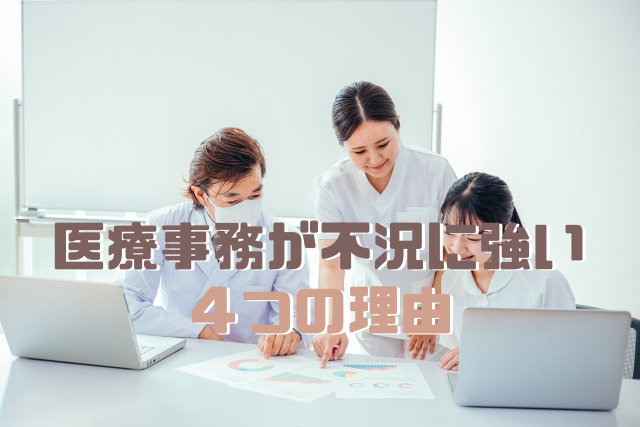

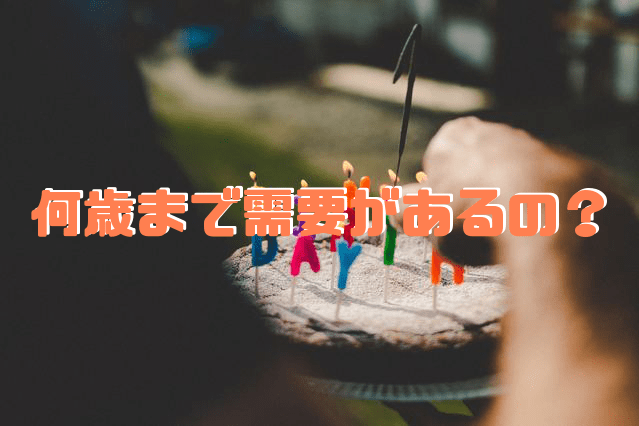












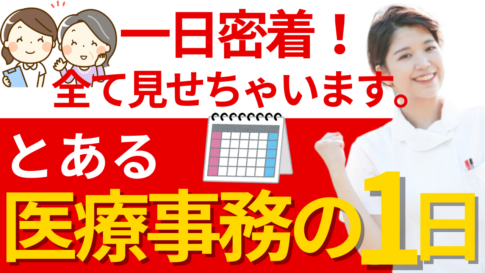
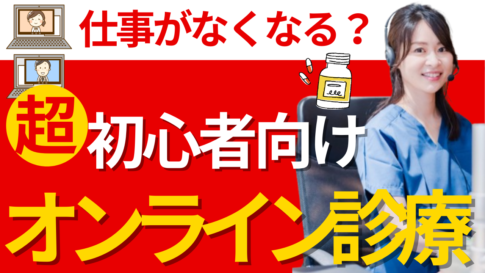


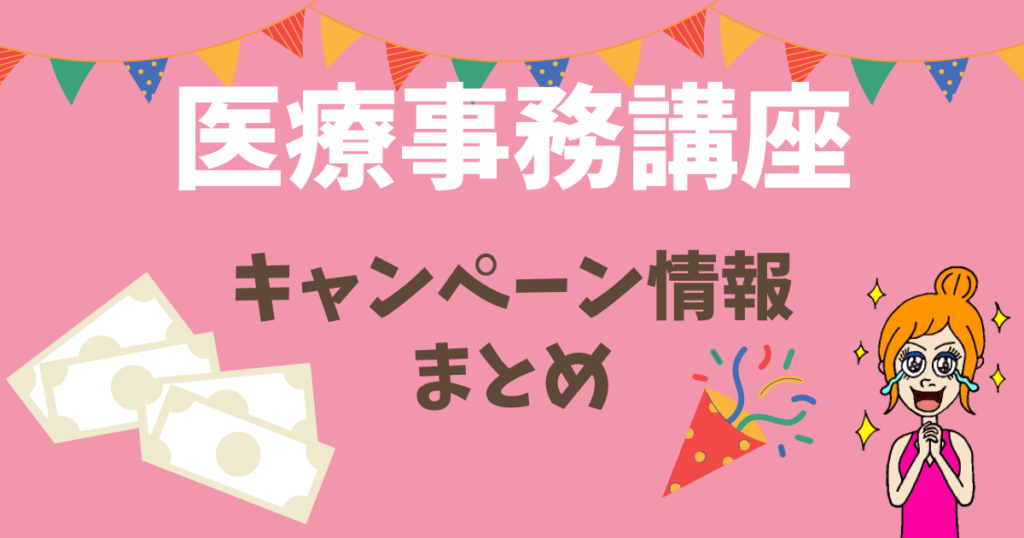
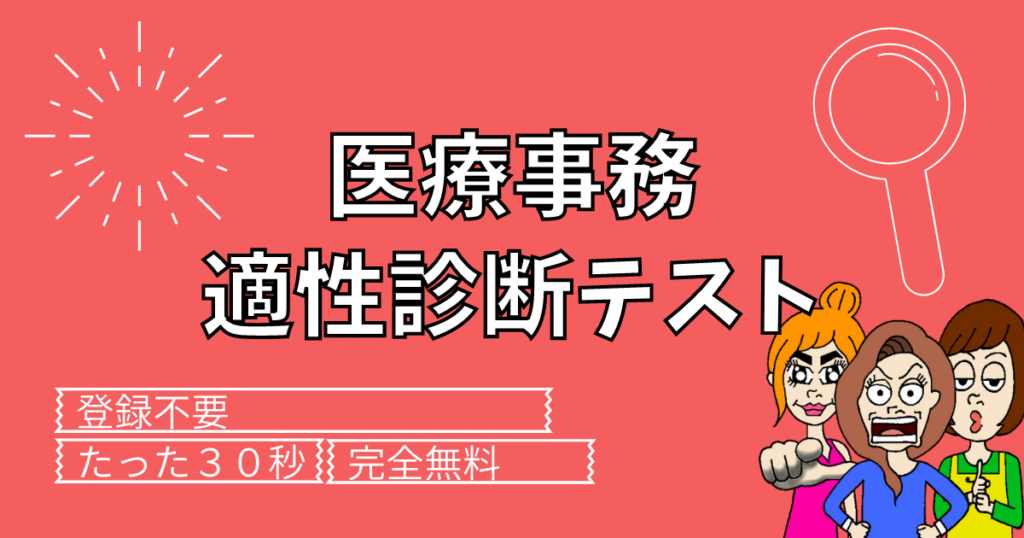
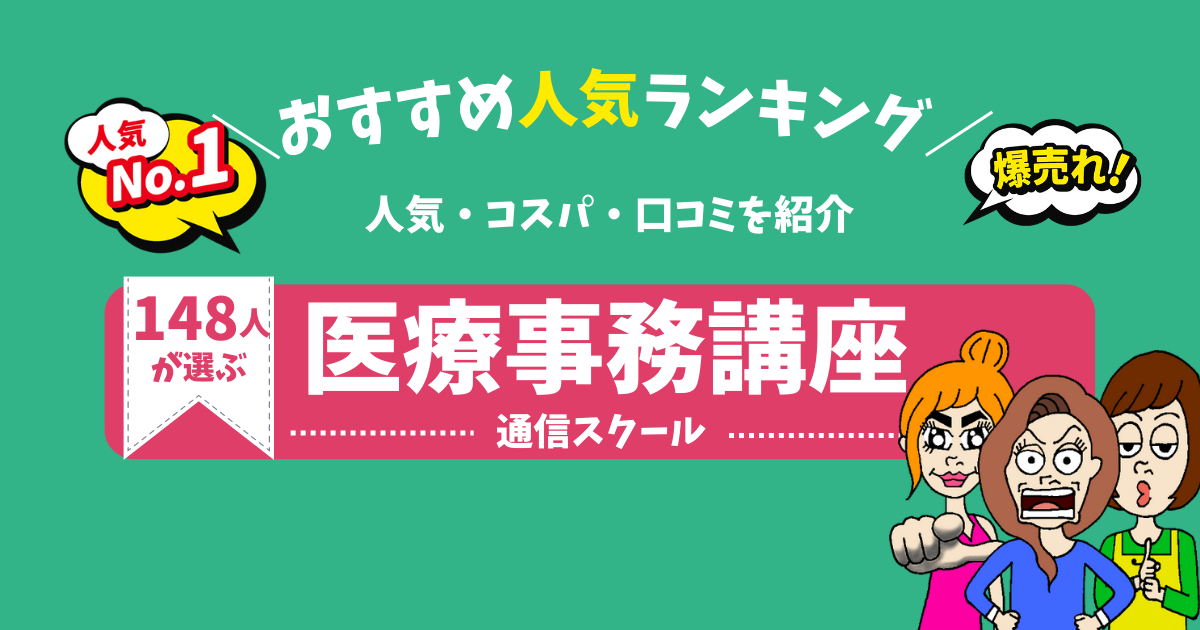
今回の記事で分かること